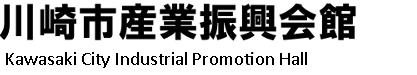無公害の超音波加工技術で無限に広がる可能性に挑み続ける

社長 内藤 勲
| 事業内容 | コンピュータ応用を中心とする電子機器・通信機器の開発及び製造 |
| 企業名 | エレックス工業 株式会社 |
| 創業 | 1976年(昭和51年)10月 |
| 所在地 | 〒213-0014 川崎市高津区新作1-22-23 |
| 電話 | 044-854-8281 |
| FAX | 044-854-8283 |
| 従業員 | 41人 |
| 代表 | 内藤 勲 (ナイトウ イサオ) |
| 資本金 | 1200万円 |
| URL | http://www.elecs.co.jp/ |
電波天文学とは一般には耳慣れない言葉であるが、光学望遠鏡では見えないような星雲などの宇宙の姿を、天体が放射する微弱な電波を捕捉、解析することによって明らかにする学問分野を指す。電波天文ではアンテナで捉えた膨大なデータを高速に信号処理するシステムが欠かせない。エレックス工業 株式会社は、コンピュータによる信号処理における卓越した技術によって世界最高レベルの信号処理装置の開発に成功するなど電波天文分野に大きく貢献している。
コンピュータの可能性を直感して起業
同社代表の内藤氏は、大学を卒業した1965年に大手通信機メーカーである沖電気工業(株)に入社する。電話交換機関連の開発部門に所属し、当時最先端であったコンピュータのハードウェア開発を志願して日々没頭していた。そのうち交換機用途での開発では飽き足らず、ちょうどその頃出現したマイクロプロセッサ(ワンチップ型の8bitCPU)を試しに使ってみた。「こんなに小さいのに十分なコンピュータとして動作する。これを使えば何でもできるはずだ」と、その汎用性を直感した内藤氏は「これからはコンピュータの時代、これは商売になる」と考えた。
当時、内藤氏は33歳で「ちょうど人生の折り返し点でもあり、この辺で将来を変えようかという気持ちになった。どこにどういう仕事があるか分からないが、マイクロプロセッサを使いこなせれば何とかなる」との思いで、まだ見ぬ需要だけを確信して1976年に電子機器の設計・製造を事業とするエレックス工業㈱を設立した。10歳程年齢の離れた部下たちも参画し、総勢4名のスタートであった。30年以上も前といえば、コンピュータの応用可能性は予想できず、金融機関の金額計算への応用がなされていた程度であった。しかし、電話交換機の開発に携わった内藤氏は、制御用に使えると確信していた。
設立当初は、採算性が上がらなかったり、連携した会社の技術力不足でプロジェクトが頓挫したりする苦労もあった。そのうちに同社の技術力が顧客に認められ、昔の上司からの誘いなどもあり、仕事が順調に増えていき、3年目ぐらいで事業として安定してきた。「起業時は無我夢中の状態であったけれど、コンピュータが流行し、エレックスで何とかできるという読みだけは当っていた」と内藤氏は振り返る。
順風満帆に進んでこられたのも、人に助けられたおかげと思っている。最初は社内に制御装置の筐体設計者がおらず、素人同然の社長自らが知人から教えを請いながら筐体設計をしていた。古巣の沖電気の人たちにも助けられた。開発を両社で協力しながら進めていった市町村向けの防災通信システムは、他社に先駆けてコンピュータ化に成功し、両社にとって大きな成果を生むことができた。防災関連事業は今でも同社の主要事業となっている。
「やってみる」の精神で入り込んだ電波天文の世界
同社は、制御システムでの実力を見込まれ、取引先からの依頼で1983年に初めて電波天文用の装置を開発した。それが国産初の相関器(複数個所から集められた電波望遠鏡データを分析、合成することで観測像を形成する装置)K3型である。最初は未知の分野で苦労した。汎用では考えられなかった20~30ギガヘルツ(1ギガヘルツ=109ヘルツ)帯という非常に高い周波数の電波を扱うには、それなりの高速応答性が求められるため回路設計だけでなく実装設計にも苦難があった。身の丈以上の依頼であったかもしれないが様々な課題を解決し、システムをまとめ上げた。「やろうと思えばできる。逃げてしまうのがやれない原因。自動車1台をゼロから作るのに比べれば楽だ」と言い聞かせた。その実績が認められ1992年に国立天文台向けの可搬型相関器を開発し天文分野へ深くかかわることとなる。2009年には、東アジア地区の観測局のデータを高速処理(取材時点で世界最大最速)できる“東アジア相関器”、そして80億回/秒の“超高速A/D変換装置”などを立て続けに発表し、電波天文における信号処理のトップ企業としての地位を確立した。天文分野に要求される仕様は世界最高レベルであり、それが同社の技術力を押し上げた。電波天文で開発した大容量記憶装置などは、様々な分野での応用が可能な技術である。それらの技術を如何に市場展開できるかが全社横断的な課題と認識している。そのためにさまざまな新しい伝送技術なども取り込んで応用可能性を模索しているところである。
良い設計を追求するための体制変更と課題設定
今後は、通信技術を使ったOEM(相手先ブランド製造)受託開発を事業の柱としていくことを構想している。そのためには、“良い設計”への追求姿勢を貫かなくてはならないと考えている。 課題は、ずばり若い世代への継承である。これは技術面だけでなく、意思決定面も含む。「どういう風に仕向けていくかは、私の宿題。2年後には引退すると公言している」とする内藤社長は2009年8月に技術者の管理体制を変えた。“本当のチーフ“を作り、自主的判断を促すのが目的である。現実問題として一足飛びに切り替えるのは難しいので、まずは判断する場面に慣れさせることから始めている。
コンピュータ関連の技術革新のスピードはどんどん速くなってきており、気がつくと踊り場に行き着いている状況もでてきている。状況打破にはブレークスルーが必要なため、設計の根本を変えなくてはならないケースにも、「やってみる」の精神で“一気”かつ“大胆”に取り組むようにしている。もちろん状況を顧みず、社長が勝手に旗を振っているわけではない。今までのレベルから判断して“つま先立ち”の状態で取り組めば解決できそうな能力を持つ社員の背中を押して取り組ませている。「つま先立ちをやらせないと人は伸びない」というのは、内藤社長の持論である。「人間の習性としてできることばかりをやってしまうと居座ってしまうので、ジョブローテーションには配慮している」と言う。また、下請けでやっているという姿勢だと意識改革が難しいので、今まで受身だった天文分野や防災分野でも、社員が自主的な発想で新製品を見つけて、張り合いをもって取り組んでもらえるように図っている。
技術開発投資は重要視している。もちろん無尽蔵の予算があるわけではない。余裕が無いなりに「今やっておかなければならないこと」に対しての絞り出しをしている。意識して絞り出さないと未来はじり貧になる。そのバランスは重要であるが、単純に数字だけで何%の開発投資をすればよいというような鉄則は無いと思っている。要は目の付けどころで「何が自分たちにとって必須なのか?」を考え、決定するようにしている。超高速A/D変換装置の開発費は自社負担したが、良い製品に仕上げれば買ってもらえるということが支えになって積極的に取り組むことができた。そういった同社の開発成果の積み重ねによって、宇宙の真の姿が一つひとつ解き明かされていくことであろう。